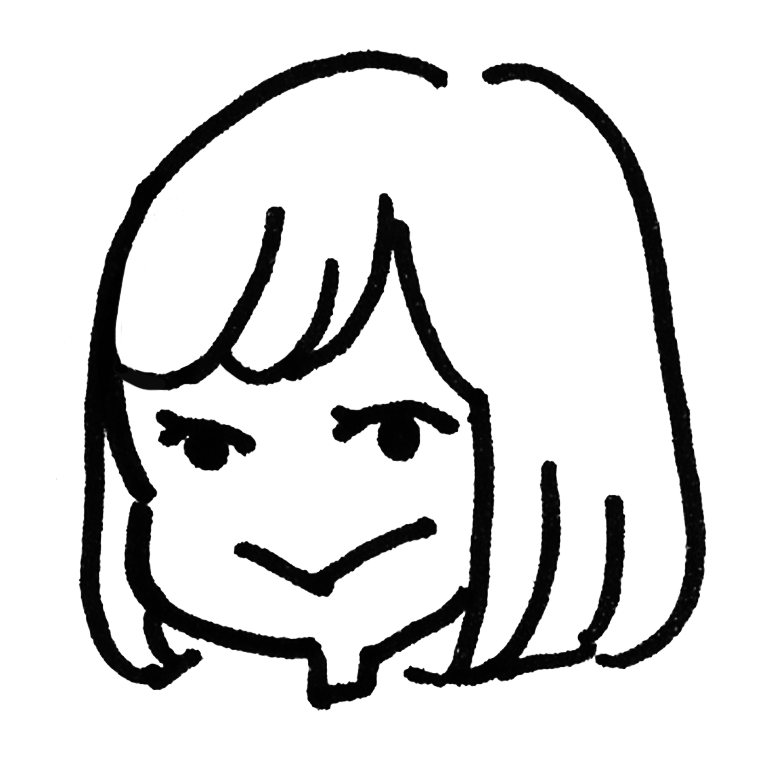多摩美術大学 統合デザイン学科の担当科目「情報編集」は、編集者として社会の中で情報をどのように読み解き、再構成し、誰に届けるか、その思考と実践を養うための講義です。
編集においては、ビジュアルを整えるだけでなく、背景にある意図や文脈、受け手にどう理解されるかまで考えることが求められます。本講義では、情報の「観察」「取捨選択」「再構成」「文脈化」の4つのフェーズを、段階的なワークとともに学びます。知識の習得だけでなく、自ら手を動かしながら構造的に考える力を身につけることを重視しています。
前期の構成と学びのステップ
1. 編集という行為の概要
講義の導入では、編集を出版やメディアにとどまらない広い概念として捉え直します。広告、サービス、製品、展示など、さまざまな事例を通じて、「何をどう伝えるか」を構造として設計する力の重要性を確認します。
2. 情報構造の理解
初期のワークでは、世の中にある無数のものを素材に、どのような軸で分類するか、グループ化するかを実際に手を動かして考えます。分類基準の違いが伝わり方に与える影響や、情報の見せ方によって受け手の理解が変わることを体験的に学びます。これは単なる整理ではありません。他者とのコミュニケーションの基盤です。そのことを理解します。
3. 要素選択と構成の設計
中盤では、情報を構成する上で重要な「入れ子構造」を理解し、設計へ活かします。同時に、文章だけでなく、図版や映像、UIなどの要素も「情報がまとうかたち」としてフラットに捉えながら、それぞれの特性を活かして最適な表現方法を選び取る練習を行います。
また、情報がまとうかたちを選び取る理由を、自らに問い直します。なぜそのかたちである必要があるのか、なぜそのタイミング(位置、順序)なのか。意味や意図がまったくなく配置される情報はない※1ということを意識付けます。
このプロセスを通して、どこまでの情報が必要か、不足や過剰はないかを検討しながら、構成の精度を上げていきます。情報を並べるだけでなく、組み立てる力を身につけることがねらいです。
4. 課題制作
展示を行うときは、会場を押さえ、展示物をつくり、告知をし、会期を経て、報告をしますよね。なにか製品をつくれば、その製品があり、パンフレットやウェブサイトをつくり、店頭に並べ、広告を出し、顧客サポートをしますよね。
情報編集ではこのように、自分たちがつくるものは一連のコミュニケーションの中にあるひとつのタッチポイントであるとしてメディアを捉えます。
その集大成として、前期課題では共通するテーマに即したリーフレットとスマホサイト※2を制作します。同じテーマといっても、こちらが提示するのは最低限の情報です。受講者はそれぞれ設定をふくらませ、特徴づけていきます。その中で生まれた細かな情報を素材に、他者に伝わる形で要素を設定し、構造化していきます。
この課題は、後期に取り組む実制作課題に向けた準備段階でもあり、「誰に」「何を」「どう届けるか」を意識しながら情報を取捨選択し構成する実践となります。
講義内で行うワーク
講義では毎回のテーマに応じて、FigJamなどを用いた演習を行います。付箋で共有し合うブレストから、分類の実践、手書きラフ、ワイヤーフレーム作成、課題のための素材整理まで、デジタル/アナログを問わず手を動かします。
コンテキストをガン見する
この講義で重視されるのがコンテキストです。
リチャード・ソール・ワーマンはコンテキストを海になぞらえました。広く周囲にたゆたう無形の存在。この海からコンテキストのひとまとまりを捉え、そこからまたコンテキストを編み出すわけです。どのコンテキストを見て、つかまえるかは、答えがひとつではありません。だからこそ、「なぜ」=設計の根拠を意識する力が問われます。はじめは自分の好みを出発点にしてもいいでしょう。
講義名を「情報編集」としたのは、私の範疇としている編集が一般的なイメージと差分を持つと考えていたからですが、前期が終了した現在、そういうことはどうでもいいかもしれんなあ、とも思い始めています。世の中の編集者は、自分がフィールドとしている場所で最適なスタイルで仕事をしていて、当たり前に多彩・多様であり、そこからスピンアウトさせて新語を主張する必要もないのではと。ここはまだ悩んでいるところです。
その一方で、英語名は “Edit and Direction” としています。これは、ミニマムな編集である切り貼りという行為に加えて、企画やアサイン、進捗管理なども編集の大事な行為と捉えたいという思いからです。これも人によっては二重の意味を持つ可能性はありますが、どちらも大事だと言いたいのです。
少し余談でした。
編集者はわからずやである
まとめると、この講義で扱う編集とは、単に情報を整えることではなく、「本当にこの伝え方でよいのか?」「どんな人に、どう伝わるのか?」と問い続ける姿勢そのものです。
編集者はなにか特定の分野の専門家ではなく、その近くにいる素人だと誰かが言っており、私も深く同意します。つまり、わからないということが原動力になるのです。そのわからずやさで、「見え方」「伝わり方」「受け取られ方」までを視界に入れると、今作っているものがどう変化しうるか?を楽しめたら、さらにその結果として新しいコンテキストをかたちにできたら、素敵なことだなあと考えています。
「よく」つくり続けるために
また、こうした編集行為は、グラフィックやUIといったアウトプットにとどまらず、展示、サービス設計、コンテンツ制作、そして組織や社会におけるコミュニケーションにも応用可能です。編集を、自分のつくるものや関わるものの意味を問い直し、方法論を見出す基盤として、この講義は位置づけられています。
編集における大まかな方法論は対象を捉えること、見立てをすることとも言いかえられるでしょう。それはものをつくるあらゆる場面で、工程ごとに顔を変えつつ生きてきます。
企画段階においては周りにただようコンテキストを、制作段階においては情報を、世に出たあとは受容のされかたを、それぞれ捉え、見立てていきます。
こうして観察・取捨選択・再構成・文脈化を回すことで、意味づけを自分で更新する能力が育つわけです。そしてこれは、いつでも自ら(あるいはチームの)指針になります。ものをつくるというタフな行為をよいかたちで持続するためには、慌てて結果を求めるのではなく、このようにプロセスを理解し組み立てるほうがずっと持続可能性が高く、ときに有効な逸脱さえ行えると私は考えています。
本講義を通して、よく(=良く、善く、能く)つくり続けるための方法論をぜひ模索していただきたいと思います。
—
※1. もし無意味であっても、それが無意味であることを意図していると考えたいのです。また、その意図には客観と主観が混じり合います。
※2. スマホサイトはFigmaのデザインファイル作成までとし、実装は必須ではありません。